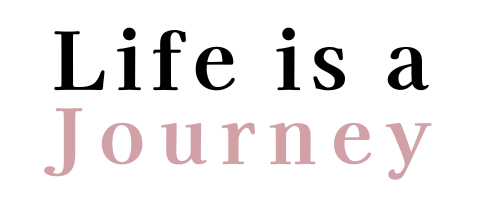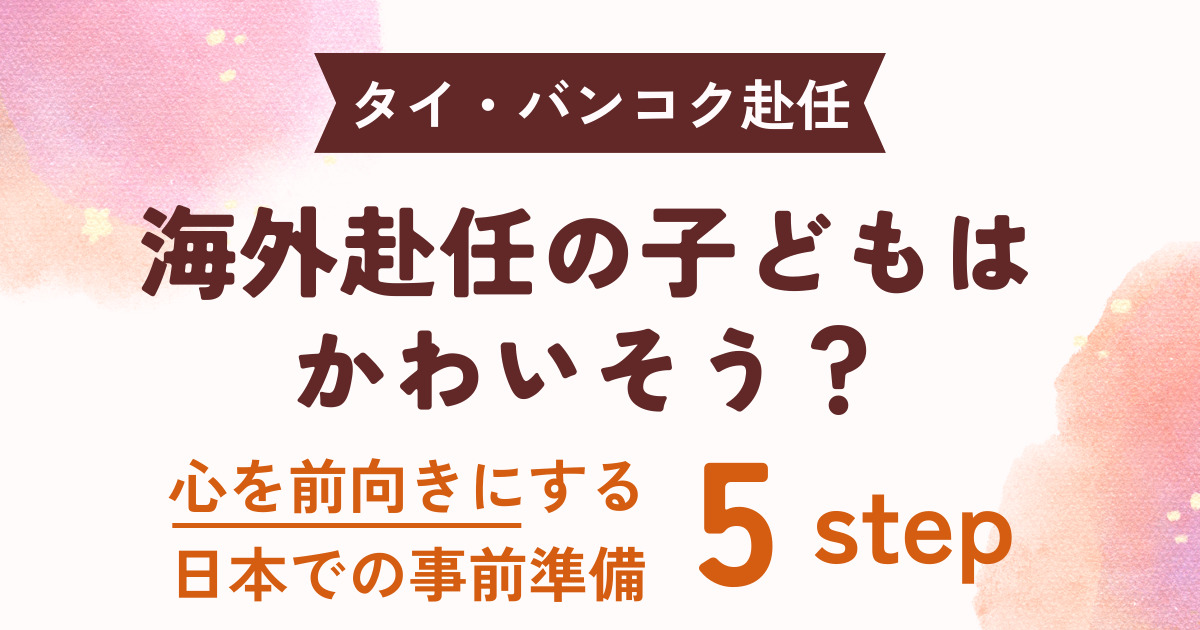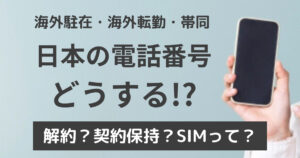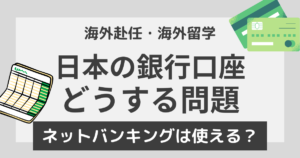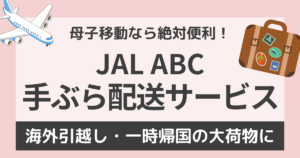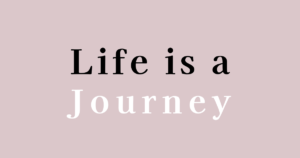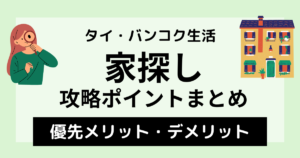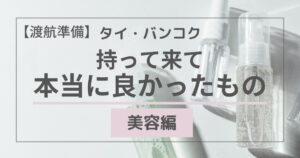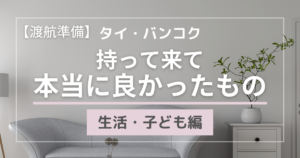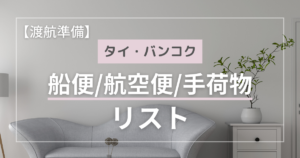「駐在が決まったけど、帯同するか悩む…」
「子ども達が日本の友達や環境と離れるのを嫌がっている…」
そんなママ達の気持ち、わかります。
我が家の子ども達(小学生と未就学児)も最初は帯同を嫌がっていたので、私もかなり悩みました。
そんなママ達へ、実際に海外駐在の帯同で2カ国に住んでみた経験と
心理士さんにも相談したのでその内容を共有しますので
少しの安心材料にしてもらえたらと思います。
 Nico
Nico我が家の場合ですが、
渡泰数ヶ月で「タイさいこー!あと何年居られるの~?」という子ども達!
もちろん今もエンジョイしています。日本もタイも大好きです。
我が家のシチュエーション
数年前にアメリカへの海外赴任も経験していますが
2人とも小さかったのでアメリカにいた記憶はほぼありません。
夫の会社は海外赴任がそうそうないので、
もう海外生活はないだろうな~と思っていた所へのタイ駐在指令。
子ども達は英語も学校や保育園で習う程度だし、不安が大きかったようでかなり嫌がっていました。
特に上の子は繊細。
転校はもちろん、目立つこと、知らない人ばっかりの環境に自分が入ること、
みんな知ってるのに自分だけ知らない状況が嫌な様子でした。
もちろんタイ行きは大反対。
別件で心理士さんのに通っていたので、
子どもへの声掛けについても相談しました。
事前準備5選
1.すぐに伝えて 時間をかけて話す


夫赴任の決定から実際の赴任まで3ヶ月弱。
夫の会社は家族の帯同は夫が赴任してから3ヶ月後というルールがあったので、
海外赴任決定から家族の出発まで半年間の準備期間がありました。
でも、未就学児はともかく小学生は学校の申し込みがあります。
日本人学校もインターも学期ごとの締め切りがあり、
国内転勤の転校のように学期途中の編入はなかなかなさそうです。
そのため、帯同するかどうかの本決定のリミットは実質3ヶ月。
期限ギリギリに子ども達に伝えるのではなく、
海外赴任が決定したら夫婦で方針を決め、すぐに家族会議開始です。
自分の思いと向き合って消化するまでの時間は子どもによって変わると思いますので
少しでも早めに伝えられた方が良いです。
また、余裕を持って心の整理をすることで、
色んなお友達とたくさん遊んだりお別れ会をする機会も十分に持つことができます。


2.選択肢と具体的な未来を示す
子供たちの性格はわかっているし、
自分が子供だったら嫌だよなぁという思いもありました。
なので大人側の都合を無理強いしないように心がけました。
選択肢を示し、どんな状況になるのかを具体的に伝えます。
- 家族みんなでタイに行く。お友達とは数年離れてしまうけど家族みんなで過ごせる。
日本に帰ったらまた同じ家に住める。 - それが無理なら、パパだけ行ってもらう。
パパとは数年離れてしまうけど、お友達と離れず同じ学校にいることができる。
本当なら夫が転職するなり海外赴任を避ける選択肢は2つではありませんが、
夫の掴んだチャンスでもあったので子供たちには言いませんでした。



この選択肢を示した子ども達の反応は「どっちも嫌!」
そりゃそうだよね。
今の時点で選ぶことが目的ではないので、それでいいんです。
バンコクなら学校も選択肢は2つ。
日本人学校に行くか、インター校に行くか。
インター校も複数ありますし、子どもの特性や希望によって選ぶことができますね。
3.とにかく寄り添って、不安な気持ちを聞く


1番大事!
子ども達の嫌がる気持ちを否定しない、軽視しない。
子どもがわんわん泣いてしまっても、
絶対に「そんなに泣かないで」なんて言わないであげてください。
「そっか、嫌な気持ちなんだね」
と穏やかに、気持ちを受け止めるようにしました。
「どんなところが不安?」
と聞いて心の中の不安を吐き出してもらいました。
幼いほど言語化は難しいですし、
言葉にするだけで何日もかかるかもしれません。
しずかに待って、不安な気持ちを吐露してくれたら「気持ちを教えてくれてありがとう」と伝えます。
嫌だと思う気持ちにとにかく寄り添う。
子どもの心に安心感が生まれます。
徐々に心の整理がついていくかと思いますが、そのスピードも兄弟でも様々。
どっちがどう、ではなくそれぞれのスピードを尊重することが大切だと感じました。
4.気持ちが落ち着いたら、不安解消を一緒に目指す
泣いて、不安を吐き出したら少しずつその不安の解消を。
言葉が通じないことが不安
我が家の場合はこれが1番の不安だったようで、
渡航まで週2で英会話教室に通うようにしました。



バンコクはインター校でなければほとんど英語は使いません。
ただ、英語は習って損はないですし、
国際的な感覚や多様性を学ぶ下準備としてもとても良い機会でした!
また、バンコクの場合は日本人学校という選択肢があるので、
それなら日本の学校と変わらないよ、ということを一緒に調べました。
転校生として目立ちたくない
私も同じタイプ。子どもの気持ちが痛いほどわかります。
バンコクにおいては日本人学校はマンモス校ですし、
インター校でも学校が合わなければ簡単に転校してしまうようなところがあるので
転校生として目立つことはほぼありません。
むしろ転校生として目立つのは帰国後!タイミングでまた悩みそうです。
習い事は継続できるか
バンコクは日本人が多いのもあって習い事もたくさんの選択肢があり、
日本の塾や音楽教室のバンコク校もたくさんあります。
この辺りは国によって変わってきますね…。
アメリカの時は日本の習い事の選択肢はほぼありませんでした。
バンコクは良くも悪くも日本人が多過くて、
大人目線としては日本とそこまで環境があまり変わりません。
(とはいえ、子供にとっては大きな変化なので決して軽視しているわけではありません)
現地校しかない国に赴任されるご家族は最初はとても大変だと思いますが得るものも多いはずです。
5.未来の楽しみを見つける
少しずつ気持ちが前に向いてきたら、赴任先のガイドブックを買って楽しみを見つけました。
行きたいところのリストアップをして、旅行気分で心晴れやか!
日本での残った時間をどう過ごすかということも子ども達と相談しました。
大好きなお友達とはお泊まり会を計画し、
じぃじばぁばと会い、お友達にお手紙を書き、お別れの挨拶のプレゼントも用意しました。
実際タイに来てみて得たもの
学校での様子


上記でも書きましたが、バンコクでは日本人の往来が激しいので転校生として目立つことはありません。
みんなが同じ立場なので、前からタイに来ていた子達は
新しく来た子達に優しく親切に接してくれます。
我が子達が学校初日にどんな顔をして帰ってくるのか心配でしたが、
ピカピカの笑顔で「あの学校好き~!」と帰ってきてくれて少し泣きそうな母でした。



先生、お友達のみんな、優しくしてくれてありがとう。
きっと我が子もその恩を誰かにパスできるはず。
子ども達が得た視点
日本にいた時は小さな社会しか知らなかったので、
世界はこんなに広いんだ、こんなに多様なんだということを知れたことが親的に良かったです。
将来につながるかどうかはまだまだわかりませんが、
異文化や多様性、自分とは違う相手を受け入れ尊重するような土台ができたのではないかなと思います。
友達とのつながり
転校が多数だと人間関係に対して希薄な思いになることもあるかもしれませんが、
一度や二度程度の転校であれば離れていても友達だと実感することができたようです。
バンコクは日本から来やすい場所でもあるので、日本の親友家族が遊びに来てくれました。
逆にバンコクで仲良くなったお友達も日本に帰国してしまう別れもありますが、
日本中にお友達がいるという風にポジティブな思いを持っているようです。
いつか私たちも本帰国になったら旅行がてら会いに行こうね!と話しています。
新しいことへ挑戦する勇気と体験
誰でも慣れた居心地の良い場所から離れる事には不安がつきものですよね。
ビジネスの場でもコンフォートゾーンとラーニングゾーンという言葉が広く使われていますが、
これと全く同じことを子ども達は体験したんだなと感じました。
ラーニングゾーンを体験し、
未知だった世界に新たなコンフォートゾーンを再構築していく様子を目の当たりにしました。
「自分には壁を乗り越える力がある」と体験できたのではないかと思います。
専門家のカウンセリングもおすすめ
今回の記事の内容が合わないタイプの子もいるかもしれません。
子どものタイプに合わせた的確なアドバイスをもらえるので、
トラウマや不登校に繋がらないために
心の専門家の心理士さんのカウンセリングを受けることもおすすめです。
\いろんなプロがいるココナラ/
ココナラの検索窓に「臨床心理士」と入れるか、
「カテゴリから探す」→「悩み相談」で探すとたくさんのプロが待っています。
直接臨床心理士の方のカウンセリングを受けるのに私は1万円/1時間かかったので、
聞きたいことを集約しておいて、ココナラで専門資格有りの方に相談するのがコスパ良さそう!



他にも社労士の方やファイナンシャルプランナーさんなど
様々なプロがいらっしゃって
気軽に相談できるので多用しています。
まとめ
海外赴任を突然言い渡された子どもはびっくりしてひどく落ち込んでしまう子もいると思います。
そんな様子を見ていると親としては「かわいそう」と悩んでしまいますよね。
子ども達にとっての大きな不安を楽しい体験に変えられないかと様々思案しました。
結果、我が家にとっては良い体験として子ども達は海外生活を思いっきりエンジョイしています!